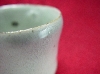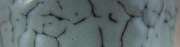粉引唐津
粉引唐津 立ちぐい 径 6.6cm 高さ 5.6cm 重さ 103g
GLKOTGH-19
粉引唐津 盃 径 9.1cm 高さ 4.4cm 重さ 111g
GLKOSGH-24
粉引唐津 盃 径 7.7cm 高さ 4.3cm 重さ 99g
GLKOSGH-40
粉引唐津 盃 径 8.5cm 高さ 4cm 重さ 86g
GLKOSGH-53
粉引唐津 立ちぐい 径 6.5cm 高さ 5.5cm 重さ 104g
GLKOTGH-72
粉引唐津 盃 径 7.5cm 高さ 4.1cm 重さ 91g
GLKOSGH-73
粉引唐津 立ちぐい 径 6.7cm 高さ 4.7cm 重さ 85g
GLKOTGH-84
多種多様な”やきもの”の中で”ぐい呑み”は、もっとも小さくて愛らしいものの一つです。
茶碗や水指、花生などの茶陶や、大きな飾壺や飾皿などに対しても一歩もひけをとらぬ人気があるのはなぜでしょうか。
その秘密の一つはやはり人の心をうきだたせたり・なごましてくれたり、時に喜びも、悲しみも共にしてくれる”洒”という名の飲み物の器だということでしょうか?
「絵唐津」とは素地に「鬼板」で、陶工の身近にある草、木、花、鳥、人物などを、指や筆で文様を描いたもので、上から「長石釉」や「灰釉」などの透明系の釉薬をかけたものものになります。
「鬼板」とは、褐鉄鉱のことで、主な産出地である瀬戸地方では鬼瓦のような形状で産出されるので、鬼板と呼ばれているそうです。
この鬼板で書いた図柄のことを「鉄絵」と言います。
「皮鯨」とは、無地唐津の口縁に鉄釉をぐるりと塗った手の総称で、なんでも鯨の皮と脂肪の境に見立てたもので皮鯨の名があるようです。大酒のみを鯨呑みと称することからもこのように呼ばれることもあるそうです。.
「朝鮮唐津」とは、黒や飴色の黒釉をかけた上から藁灰釉(わらばいゆう)を流し、釉色の変化を表現したもの、またはこの2つの釉をかけ分けたものをいいます。
一般的には、鉄釉を下にかけ、わら灰釉を上から流し多ものが多いのですが、逆にかける場合もあります。
「三島」とは器がまだ生乾きのうちに、印花紋、線彫、雲鶴(うんかく)等の文様を施し、化粧土を塗って、削りまたは拭き取り仕上げをした後に、長石釉や木灰釉をかけ、焼き上げたもので、象嵌(ぞうがん)の一種です。李朝三島の流れを受け継いでいるので三島唐津というそうです。
「粉青沙器」とは「粉粧灰青沙器(ふんしょうかいせいさき)」の略語で、李朝時代の15~16世紀にかけて作られた、『白化粧を施した上に青磁釉を掛けた陶器』を意味します。
「梅花皮」とは、土と釉薬の収縮の差からうまれ、「釉薬が 粒状に縮れた状態」をいいます。
名前の由来は、刀の鞘に用いられる鮫皮の一種を、本来梅花皮と呼び、粒状の表面が似ているところからの呼び名のようです。
「窯変」とは文字どうり、窯に入れた時の火の具合によって、通常の釉調とは異なる反応がおきる自然な色の変化を指します。
そのため、一点毎に焼き上がりの色合いは異なり、全く同じものは二つできないことになります。
「古唐津風-青唐津」は、あくまでも私個人が作った古唐津風なぐい呑みです。土や釉薬を「当時はこのようにして作ったのではないだろうかと試行錯誤して作ったぐい呑み作品です。主に青唐津を作っています。
「古唐津風-山盃」は、あくまでも私個人が作った古唐津風な山盃です。
轆轤成型を終えた器はまず糸を使って土より切り離します。切り口は糸切り痕となります、唐津の山盃は雑器として作られたものなので高台は作られていないようです。
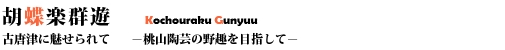

 前のページへ
前のページへ